琵琶湖のそばを流れる瀬田川で、「アメリカナマズ(チャネルキャットフィッシュ)」という外来魚が急に増えているのを知っていますか?
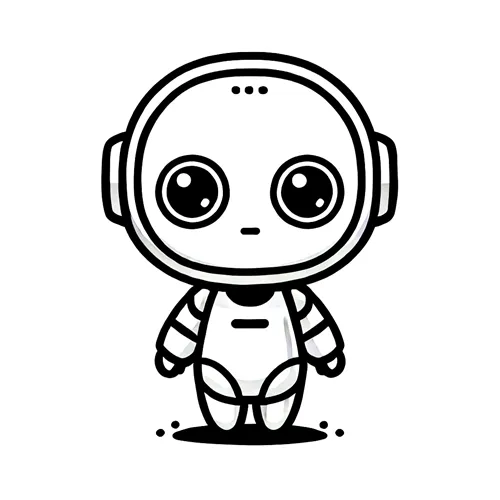
さらに、茨城県の霞ヶ浦では、昔からたくさん獲れていたワカサギやシラウオが減り、その背景にアメリカナマズの「食べ過ぎ」が関わっていることが分かってきました。
この記事では、アメリカナマズが日本の湖で起こしている変化を「科学目線」で分かりやすく紹介します。
アメリカナマズについて

アメリカナマズはどんな外来魚?
アメリカナマズ(チャネルキャットフィッシュ)は北アメリカ原産のナマズの仲間で、日本のナマズより細長い体つきが特徴です。
口のまわりには複数の「ヒゲ」があり、暗い水の中でも匂いや振動を感じとって餌を探せます。
とくに注目されているのが、食性の幅広さです。
- 幼魚:水生昆虫、エビ、小さな甲殻類
- 成魚:小魚、カエル、貝類、魚の卵
- 暗い場所でもヒゲで餌を感知して捕食できる
このように「食べられるものが多い」ことが、生態系への影響の強さにつながっています。
日本にはどうして入ってきた?
アメリカナマズが日本にやってきたのは1970年代。
最初は食用・養殖・スポーツフィッシングを目的に導入されました。
しかし、
- 養殖池からの逸出
- 釣り場として放流された個体が野外へ定着
などが重なり、霞ヶ浦水系を中心に分布が拡大しました。
環境適応力が高く、水温や水質の変化にも強いため、「一度広がると止めるのが難しい」外来魚として知られています。
なぜ“強い影響を与える外来魚”とされるのか
自治体がアメリカナマズを警戒している理由は、次の3点に集約できます。
- 捕食による直接的な影響
小魚やエビ、卵など在来生物を広範囲に食べてしまう。 - 餌・すみかの競合
ウナギ・コイ・フナなど、同じ水域の魚と資源を奪い合う可能性がある。 - 産業・作業への影響
背びれや胸びれに鋭いトゲを持つため、漁師の作業でケガが起きやすい。
アメリカナマズは、生態系の仕組みそのものに変化を起こす可能性を持った外来捕食者です。
では、この魚が琵琶湖や瀬田川で実際にどのような広がり方をしているのでしょうか。次は、現地で起きている最新の動きを科学的に見ていきます。
琵琶湖・瀬田川で何が起きている?

滋賀県・瀬田川のほとり
瀬田川で数が急増している理由
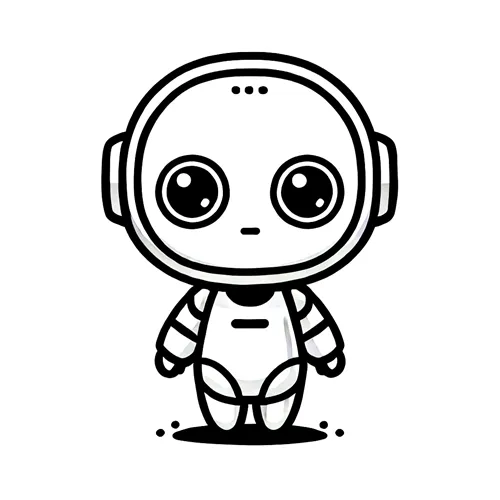
琵琶湖では、アメリカナマズの確認は2001年に初めて生息が確認されました。
近年、琵琶湖から流れ出る瀬田川で急に数が増え、滋賀県が警戒を強める状況になっています。
増加が目立つ大きな理由は、瀬田川がアメリカナマズにとって住みやすい環境になっていることです。
川底にはエビや小魚などの餌が多く、流れがゆるむ場所もあり、産卵のための隠れ家にも適しています。
また、温暖化によって水温が高めに推移することも、北米原産のアメリカナマズには有利に働いている可能性があります。
琵琶湖への拡大がもたらす生態系への影響

琵琶湖
瀬田川で数が増えると、そのまま琵琶湖へ広がるリスクが高まります。
琵琶湖にはフナ、アユ、モロコなど、多くの固有種や在来魚がすんでいます。
もしアメリカナマズが本格的に入り込めば、餌の奪い合い(競合)や小魚の捕食により、生態系のバランスが大きく変わる可能性があります。
とくに小型の在来魚が減ると、それらを食べる鳥類や他の魚にも影響が広がり、食物連鎖の「連鎖的な変化」を引き起こすことが懸念されています。
漁業現場で起きている問題
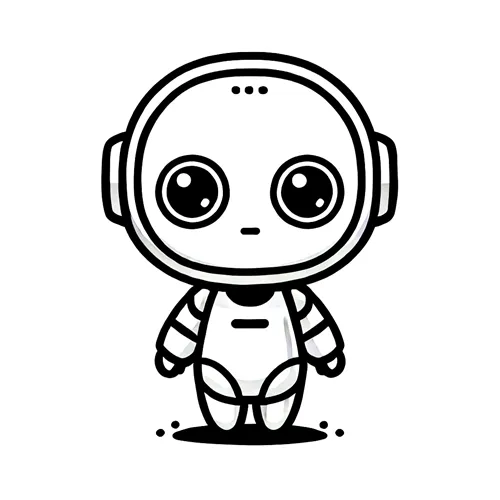
アメリカナマズが増えると、漁業への負担も大きくなります。
背びれや胸びれには鋭いトゲがあり、漁網から取り出す際に手を刺す危険があるため、漁師の作業リスクが高まります。
また、外来魚が網に多く入ることで漁獲作業の手間が増え、仕事量そのものが増加するという問題も起きています。
このように瀬田川で起きている増加は、生態系・在来魚・漁業への複合的な影響が同時に進んでいるサインといえます。
そして、アメリカナマズが増えたときに起こる変化をより明確に示しているのが、霞ヶ浦で見られる「ワカサギの減少」です。
次は、その科学的背景を詳しく解説します。
霞ヶ浦でワカサギが減っているのはなぜ?

ワカサギの減少とアメリカナマズの関係
茨城県の霞ヶ浦では、かつてワカサギやシラウオが豊富に獲れていました。
しかし近年、漁獲量が大きく減少し、地元の漁師にとって深刻な問題となっています。
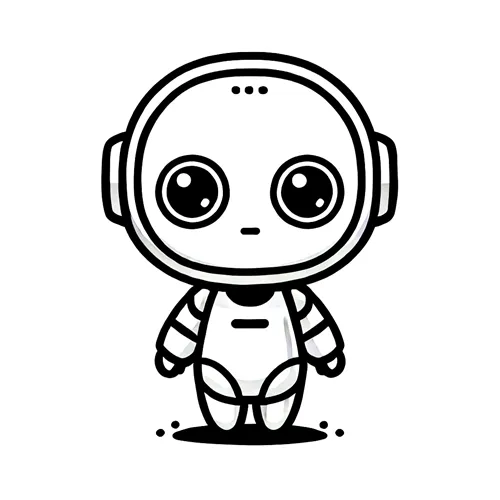
その背景のひとつとして注目されているのが、アメリカナマズによる捕食と横取りです。
アメリカナマズは雑食性ですが、成長すると小魚やエビを積極的に食べるようになります。
実際に霞ヶ浦で採取されたアメリカナマズの胃の中からは、ワカサギの成魚や稚魚が多数見つかる事例が報告されています。
ワカサギは体が小さく群れで泳ぐため、動きに反応して捕食するアメリカナマズにとっては狙いやすい餌になってしまうのです。
定置網の中で起きる「横取り」
霞ヶ浦では定置網を使ってワカサギを漁獲しますが、その網の中にアメリカナマズが侵入し、捕れたワカサギを満腹になるまで食べてしまうケースがあります。
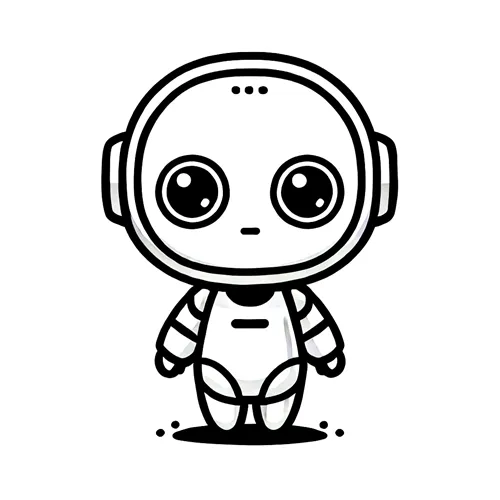
漁師が苦労して集めた漁獲物を網の中で食べられてしまうという状況が実際に起きています。
この横取り行動は、漁獲量の減少を直接的に引き起こす大きな要因のひとつと考えられています。
減少の原因は「ナマズだけ」ではない
ただし、ワカサギの減少が「すべてアメリカナマズのせい」というわけではありません。
霞ヶ浦では、水温の上昇、水質の変化、流入河川の環境悪化など、複数の要因が同時に進行しています。
ワカサギは環境変化に敏感な魚であるため、これらの要因が重なって資源量が大きく落ち込んでいると考えられます。
つまり、霞ヶ浦で起きているのは、外来魚による食害と湖の環境変化が重なった複合的な問題です。
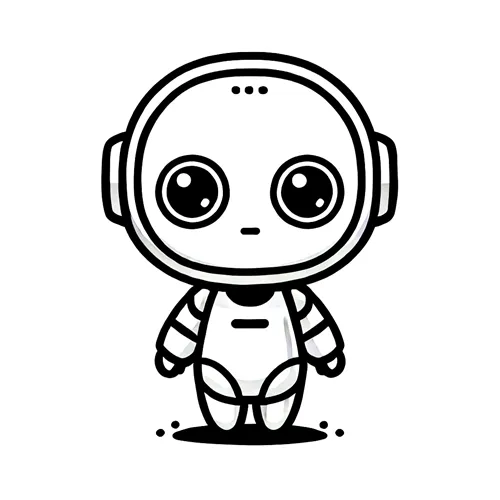
アメリカナマズはその中でも影響が大きい要因のひとつであり、ワカサギの減少を加速させている存在として問題視されています。
ワカサギが減ると生態系に何が起きる?
ワカサギは多くの魚や鳥の餌になる重要な「中間の位置」にある魚です。
数が減ると、ワカサギを食べていた生き物が影響を受け、湖全体の食物連鎖がゆらぎ始めます。
では、生態系はどう変化していくのでしょうか。次は、この問題を「食物網」と「生態系バランス」の視点から科学的に考えていきます。
アメリカナマズが増えると、生態系はどう変わる?
生態系に起きる「カスケード効果」とは?
アメリカナマズのような上位捕食者が新しく入り込むと、湖の生態系は連鎖的に変わり始めます。
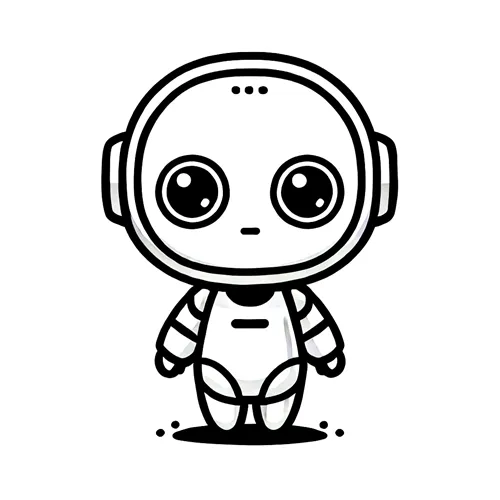
これは科学で「カスケード効果(連鎖効果)」と呼ばれ、ひとつの生物が増えたり減ったりするだけで、別の生き物にも次々と影響が広がる現象です。
たとえば、ワカサギのような小魚が減ると、それを餌にしていた魚や鳥の食べ物が足りなくなります。
エサが減れば個体数が下がり、さらにその魚を食べる別の動物にも影響が出るなど、食物連鎖の「ドミノ倒し」のような変化が起こります。
広い「食べる範囲」が崩してしまうバランス
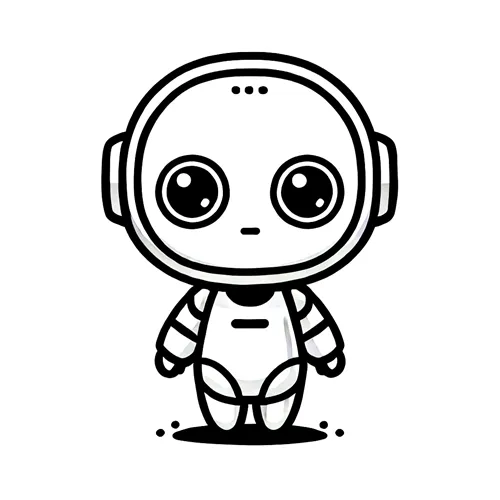
アメリカナマズが厄介なのは、「食べる量が多い」だけでなく、「食べる相手がとても幅広い」ことです。
小魚、エビ、カエル、貝、さらに魚の卵まで食べてしまうため、本来なら別の役割を持つ多くの生き物が一斉に減ってしまいます。
その結果、魚同士の関係や食物網のつながりがいろいろな場所で乱れ、複数の生き物のバランスが同時に崩れやすくなるのです。
在来魚との「見えにくい競合」
もうひとつの問題は、在来魚との競合です。
アメリカナマズと同じように底生のエビや小魚を食べるウナギやコイの仲間は、餌が少なくなると成長が遅れたり、数が減ったりします。
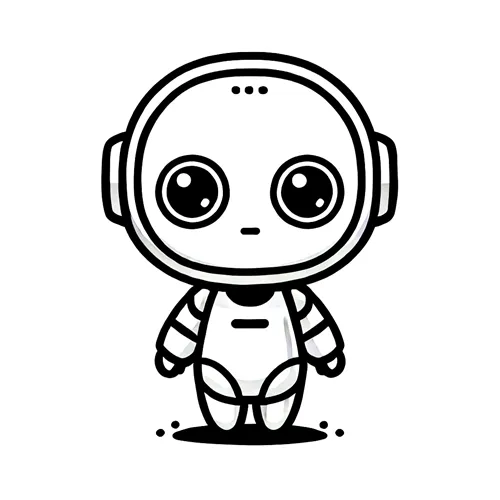
こうした競合は、目に見える「食べられる被害」ほど分かりやすくはありませんが、長い時間をかけて在来魚の資源量をじわじわと減らしていくおそれがあります。
湖そのものの性質が変わることも
外来捕食者によって在来魚が減ると、「湖の働き」そのものが変わることもあります。
たとえば、小魚が少なくなるとプランクトンを食べる生き物が減り、結果としてプランクトンが増えすぎることがあります。
すると水が濁りやすくなったり、透明度が下がったりして、水草が育ちにくくなるなど、水質や水中環境の変化につながることがあります。
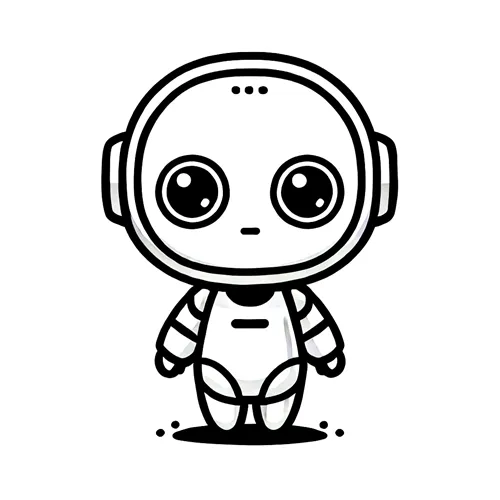
このように、アメリカナマズが増えることで起こるのは、魚種の減少にとどまらず、 生態系全体がゆっくりと形を変えてしまう構造的な変化だと考えられています。
では、こうした外来魚による変化に対して、私たちはどのように向き合えばよいのでしょうか。
次は、アメリカナマズへの対策や、地域で行われている取り組みを科学的な視点から紹介していきます。
外来魚とどう向き合う?

まずは「今、何が起きているか」を知ることから
アメリカナマズが増えると、湖や川の中でどんな変化が起きているのかを正しくつかむ必要があります。
そのために行われているのが、定期的な観察(モニタリング)です。これは、生態系の「健康診断」のようなものです。
琵琶湖や霞ヶ浦では、研究者や自治体が次のようなことを記録しています。
- どこで、どれくらいアメリカナマズが捕れたのか
- 体の大きさや年齢の分布
- 何を食べていたのか(胃の内容物の調査)
- 在来魚の数がどう変わっているか
こうしたデータを積み重ねることで、「どの地域で影響が大きいのか」「ワカサギがどれくらい減っているのか」といった現状が見えてきます。
外来魚への対策は、この情報が土台になっています。
捕獲による数のコントロール
現在の対策の中心は、アメリカナマズを捕獲して数を抑える取り組みです。
広い水域では完全にいなくするのは難しいため、在来魚の減少を少しでも防ぐことを目標に、地道な作業が続けられています。
「食べて活用」はどう考える?
アメリカナマズは北米では食用として利用されてきた魚で、日本でも「食材として活用できないか」という意見があります。
ただ、利用だけで大きく数を減らすことは難しく、「食べれば解決」だけでは無理があります。
外来魚の対策として利用を考える場合でも、観察(モニタリング)や駆除と組み合わせ、科学的に管理していくことが欠かせません。
一人ひとりにできること

外来魚の問題は遠い話に聞こえるかもしれませんが、私たち一人ひとりの意識と行動が、地域の自然を守る力になります。
私たちが今すぐできる、具体的な行動は以下の3点です。
- ⚠️ 決して放流しない:飼っていた魚や水草、外来生物などを「絶対に」自然の水辺(川、池、水路など)に放さないでください。
- 🎣 釣り場のルールを守る:外来魚の再放流禁止など、釣り場や自治体が定めたルールは必ず守りましょう。
- 💡 正しい情報を確認する:外来魚に関する最新の情報や、駆除・対策ルールについて、自治体や研究機関などの信頼できる情報を常に確認しましょう。
日々の小さな行動こそが、地域の豊かな生態系を守る大きな力へと繋がります。
外来魚問題から見えてくること
アメリカナマズとワカサギの話は、生態系のバランスがどれほど繊細なのかを教えてくれます。人の活動と自然がどのようにつながっているのかを考えるきっかけにもなります。
次のまとめでは、この記事で取り上げたポイントを整理しながら、外来魚問題を理解する意味をあらためて振り返ります。
まとめ:アメリカナマズから見える「生態系のつながり」

アメリカナマズが増えている地域では、ワカサギや在来魚の減少、漁業への負担など、さまざまな変化が重なって起きています。
ひとつの原因だけで説明できる問題ではなく、「食べられる」「競合する」「環境の変化に弱い」など、いくつもの要素が影響しあっています。
- アメリカナマズは食べる相手が幅広く、生態系に入り込むと影響が広がりやすい
- 琵琶湖の瀬田川では増加が目立ち、拡大を防ぐための対策が続けられている
- 霞ヶ浦ではワカサギの減少に、アメリカナマズの捕食や「横取り」が関わっている
- 外来魚の影響は、食物網や在来魚との競合など、目に見えにくい部分にも広がる
- 対策には、定期的な観察(モニタリング)と捕獲が欠かせない
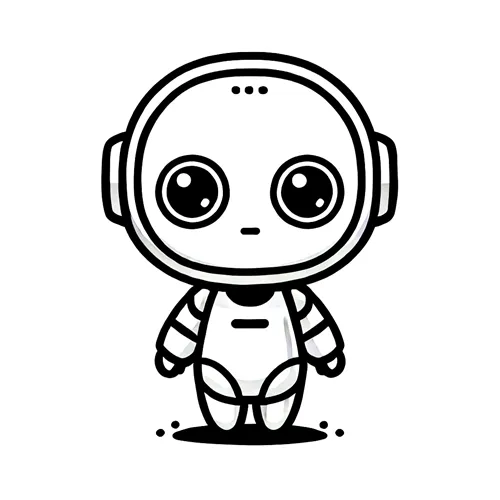
外来魚の問題は、生態系のつながりを理解するうえでとても大切なテーマです。ワカサギやアメリカナマズを通して、自然のバランスがどれほど繊細かを知ることができます。
私たちの身近な行動「外来生物を放さない、正しい情報を確かめる」といった小さな一歩も、長い目で見れば自然を守る力になります。
今回の内容が、湖や川の生き物たちの「見えないつながり」を考えるきっかけになれば幸いです。



